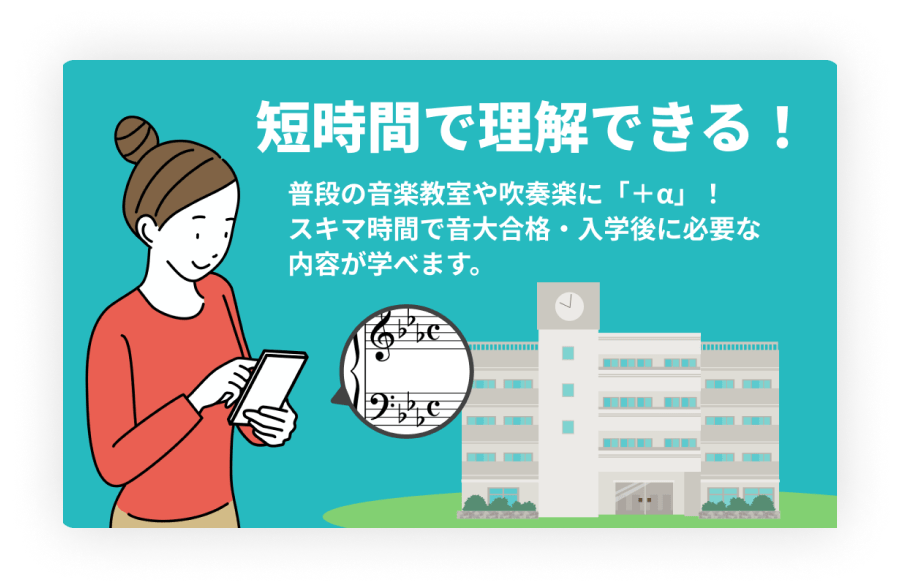西下航平さん
2018-11-24
今回ご協力いただきましたのは、作曲家の西下航平さんです。
音大と一般大を並行して受験するという、異色ともいえる受験体験をお持ちの西下さん。 受験について、そして作曲について、ご自身の経歴やお考えをお話して下さいました。
西下さんは宮城のご出身と伺いましたが…
宮城は生まれてから少ししか住んでいなくて、その後千葉、埼玉、そして小学生から1浪する19歳まで石川…と色々な所に移り住んでいます。
では石川には長く住んでいらっしゃったのですね。その後大学進学を機に上京されたということでしょうか?
はい。
大学受験は、東京音楽大学の作曲科と、東京学芸大学の中等教育音楽科を声楽で、あと東京理科大学も受験して、合格しました。
なんと壮絶な受験体験…!それまでの音楽歴についても教えて下さい。
一番最初に音楽を習い始めたのは埼玉の南浦和にいるときで、近所にあったヤマハに通っていました。
両親も幼少のころピアノを習っていたこと、たまたま近所に教室があったことなどが理由で、習い始めたようです。
それと、初めてレッスンに行った時、私がすごく音楽に反応したらしくて。先生に「絶対に音楽をやったほうがいい!」と勧められました。
石川に移ってからはエレクトーンを習い始めて、その後ピアノを習いました。
高校を出てから、受験のために作曲と声楽の先生に師事したという形です。
なるほど。ピアノ歴についてもう少し詳しく教えて下さい。
最初にピアノを習った先生がご結婚されてからは、菅井千春先生に習いました。
ピアノの先生でしたが作曲も教わりました。
ピアノの先生が作曲も教えるとは驚きです、バイタリティある先生だったんですね。
作曲の活動としては、ヤマハにJOC(ジュニアオリジナルコンサート)というのがあり、私は小学1-4年の時に出場していました。
けれど、自分で書いた曲を弾くのが嫌で(笑)
ピアノはあまりうまくなかったし、難しい曲を書いたとしても弾けないしで、やめちゃいました。
作曲自体はそのあともちょこちょことやっていましたが…そのあとちゃんとやり始めたのは中学校の自由研究ですね。
中学校の自由研究!懐かしい響きですね。
自由研究をするのが面倒臭くて、だったら作曲をすればいいのでは?と。
そうして作曲して、多重録音を駆使してレコーディングをして、無事金色の短冊を貰いました(笑)
先生もびっくりしたのではないでしょうか。その後、ピアノのレッスンはどのように進んでいきましたか?
それこそ、バッハのインヴェンションやシンフォニアを進めていったのでしょうか?
シンフォニア、全然やらなかったですね〜。
実は学芸大を声楽で受けたのもそれが理由でした。ピアノだと長年習ってきた人と張り合わなきゃいけないけれど、声楽ならこれから頑張れば追いつけるかもと思いまして。
その分、インヴェンションは15曲全部弾いてから得意な曲を選び、完璧にして試験に臨みました。
先生は「バッハをやりなさい」とか、これをしなさいとか、あまりうるさい人ではなかったのでレッスンを続けられたのだと思います。
他にも、自分は手が大きかったので、ショパンとかラフマニノフ、ドビュッシー等も弾きました。
なるほど、面白い先生ですね!
コンクール等もたまには出ていましたが、先生に強制されるでもなければ、自分が好きでもなかったですし。
そういう緩さがよかったんだと思います。
バッハにしろコンクールにしろ、後から考えれば、幼いうちにやっておけば良かったという人もいるかもしれません。
けれど当時そればかりやらされていたら、絶対に私は音楽を辞めていたと思います。これは私の考えですが、いつでもやりたくなった時にやればいいんだと思いますよ。
長い目で見て、生徒がずっと音楽と付き合っていくことを考えると、そういう指導の形も素敵ですよね。
そうですね。
もし自分が先生の立場になってぶっちゃけ自分の生徒に音大進学を勧めるっていうと…うーん。
なんというか、音大という環境の使い方を間違えないでほしいと思いますね。
というのも、音大に進学してびっくりしたのですが、知的好奇心のある人が少ないんです。
えっ、それは意外なご意見です。
本当に!(笑)
周りを見ていて思うのが、一線で活躍できるような人は頭が良い人(≠勉強ができること)だということです…だいたい。
それか、抜きんでて何かを持っている人。
好奇心は、音楽をやる上で大切です。
色々なことにアンテナを張って、いかに自分にとって新しい情報を得ようとするか、というのが大切だと思います。
そういった意味では、音大付属高校も善し悪しで。確かに音楽に集中できる環境を得ることはできます。
けれど、例えば数学はⅠAまでしかやらないんですよ。それって、貴重な学びの機会を失っているともいえますよね。
世界史や地理、化学や数学、もちろん文学も音楽に通じる部分があるのに。
そういった勉強をおろそかにして音大に来ても、何の意味もないと思うんですよね…。
色々な知識をもって、音楽の業界のつながりや練習環境を整えて、自分の目標に向かってまい進する場所が「音楽大学」だと思います。
無目的に来るには、あまりにも危険すぎる場所です。
一般大学なら多少無目的でも道はひらけますが、音大ではつぶしがききませんから。
音大にいることで視野狭窄になる可能性をきちんと理解して、リスクマネジメントをしないと、大変なことになります。
私は、音大を目指す高校生にはこのことを伝えています。それで進学をやめるなら、その選択も正しいと思います。
ピティナの特級グランプリを東大生が取るし、三善晃も武満徹も音大出身ではないし。
というのも、ピアノや作曲家は一人ですることだからだと思います。
弦楽器などは、プロのオーケストラに乗ることを考えると、ある程度の基礎は第三者によって裏打ちされてないといけません。なので、その保証として「音大卒」というのは必要かと思いますが。
楽器によっても考え方は違うということですね。「音大卒」のメリットとリスク…よく考えなければいけませんね。
今、日本の音楽大学はある種のパラダイムシフトを迎えているのかもしれませんね。
そもそも子どもの数が減っているのに、一年で学費が200万円は掛かりますからね…東大をはじめとする国立大学に4年通えますよ。医学部も出ることができます、しかも医学部を出れば医者になれますが、音大を出ても普通何の資格も付きません。
だから、レベルを下げて有象無象の生徒を取るのか、レベルを保つためにふるいにかけるのか、音楽大学は選択を迫られました。
そんな中、藝大(東京藝術大学)は人気を維持していますが、入学試験自体は易化しているように感じます。個人の感想なので当てにしないでくださいね。だいいち受けたことはないし、当時受けたとしても、下手すると今受けたとしても受かる自信はありません(笑)
作曲でいうとフーガの試験がなくなったんですよ。
フーガの試験についてはよく議論されますね。フーガを試験することは、作曲科志望の生徒を篩にかけるということですか?
はい。
そのためには、フーガというものが何かを知る必要があるわけですが…。
フーガというのは、基本的に線と線の重なりなんですよね。
例えばポップスおいて、楽曲中の声部が主旋律とその伴奏という関係を持って成り立っています。
しかし、フーガはどちらが主旋律でどちらが伴奏かなど、そういった関係は持っていません、メロディーの重なり合いで1曲が出来ています。いわば、「機織り」みたいなものですね。
バッハが凄いのは、その「機織り」を、秩序の下で、ありとあらゆる編成で、破綻なく作っていることです。
最大で5声もあるフーガの曲が、なんとチェンバロで書かれていたりします。5声という声部の多さもさることながら、それを両手で弾けるようにするのって、凄いですよね。もうバケモンです。
そのフーガの考え方は現代まで受け継がれています。
例えばマーラーは長大な曲の中で「フゲッタ」いう小規模なフーガを曲中で用いたりします。ほかの作曲家の楽曲の一部にも、フーガ的な曲想っていうのは出てきますよね。近代だとショスタコーヴィチの曲なんかにもでてきますよね。
ああいう曲って、対位法の知識や技術なくして書けないわけです。一番簡単に言うと合いの手です。旋律を反行させたり逆行させたりすることで、複雑に、小難しくともいいますが、クラシカルなものになるわけです。
でもそれを教えられる人がいなくなってきている。もちろんある程度の、例えば藝大の先生なら教えられるとは思いますが。
旋律線の破壊が歴史とともに進んできて、新ウィーン楽派、ケージによって偶然性の音楽が市民権を得たり、ヘンリー・カウエルの作品にみられるようなトーン・クラスターの多用、シュトックハウゼンからこっち、録音技術の発展によるテープ音楽、コンピュータミュージックの台頭…そのなかで旋律線というのは必然ではなくなってきたんですね。
そうなると、今まで作曲の一技法であった対位法は、既存のものでは対応できなくなってきたわけです。旋律線がないのですから、対位法自体の存在意義が薄れてしまいます。
あとは単純に聴衆の耳がついてこなくなった。耳なじみのいい曲につられていくわけですよ。
フーガってものは聞き取りにくいですよね、どれがメロディって必ずしも分かるわけではないですし。
時代から必要とされなくなった対位法は、フーガの試験として実施する必要が無いという判断なのでしょうか。それとも大学に入ってから充分にフーガを学べばよいということなのでしょうか。本来であれば電子音楽であろうが、音高のない打楽器の音楽であろうが対位法という考え方自体は必要だとは思うのですが…
なるほど、時代背景を鑑みて試験の内容も変わっているのかもしれませんね。
作曲業界、とても奥が深いですね…。
今作曲をやってる人は、作曲だけに集中する時間的なリソースがないんですよ。
締め切りに追われバイトをし…そんな状態ではいい曲なんて書けません。
ものを生み出すには時間がどうしても必要なんですよ。
更にはプロのオケですら新しい曲を必要としないので、オーケストラ曲を作曲する機会もないですし。
戦後の音楽復興において藝大は大きな功績を上げたと思いますが、小難しい曲を作らなければいけないという風潮を作ったことは罪ともとれます。
小難しい曲がコンクールに好かれるし、ロマン派的な旋律を書くことを、まるで全裸で歩くみたいに思われたりします(笑)
規則を破壊してなんぼと思う気持ちは共感できます。だからといって最初から壊そうとするのは大変なことです。
これは歴史的な要因もあると思います。
日本で初めて交響曲を書いたのは山田耕筰でしたが、当時のドイツで現地の「今の」音楽に触れてしまった。これはある意味パンドラの箱で、いったん触れてしまえばもう戻れない。過去の古めかしい音楽は雲散霧消し、日本における西洋音楽もこの時代のものについていくことを余儀なくされたわけです。とは言え海外に手軽に行けるようになったこの時代、遅かれ早かれそうなったとは思いますが。
そうして自国での積み重ねなく、ただ近現代の曲を見よう見まねで書いても、海外から評価は受けられないと思います。
現に世界で評価されている日本の楽曲は、日本の民族性をたっぷり生かした曲ですよね。武満のノヴェンバーステップスだったり黛敏郎の涅槃交響曲だったり。西洋音楽の真似事ではやっぱりかなわないんです。
本場の物に勝とうと思ったら正統に経験を積んでいかなければなりません。バッハから続いてきた伝統を、本当は日本でも恥ずかしがらずに積み重ねていく必要があるのだと思います。その点日本の音楽、つまり邦楽についてはそういった伝統があると思うのですが、今や吹けば消えてしまいそうな風前の灯火です。
私が割と正統派な曲を書いて発表し続けているのは、そういうことにもささやかながら取り組みたいからです。
ちゃんとメロディーが分かる、口ずさめる、形式感もすこし気にした曲です。
真っ白なキャンバスに絵の具がどばーっと撒かれたような芸術がもてはやされたこともありましたが、今はそうではなく、何かに裏付けられたものがないと、評価はされないと考えています。
西下さんの考えは楽曲にも表れているんですね。
ところで西下さんは作曲以外にも色々なさっていますね。
はい。作曲家なら色々な楽器をやっておきたいなと思って。
親に懇願して通わせていただいたので、大学を使い倒してやろうと思い、まず最初に薩摩琵琶を始めました。
あと吹奏楽のサークルでトロンボーンを吹き始め、教職課程のオーケストラの授業でヴィオラもやりました。トロンボーンとヴィオラは今でも演奏します。
ほかにも打楽器、チューバ、ユーフォ、エレキベース、ジャズに指揮…
凄いです、沢山なさったんですね。
作曲する上では無駄にはならないと思って色んなことをしましたね。器楽科の友達に楽器の奏法やコツを教えてもらいながら試行錯誤しました。
編曲も沢山やりました。
1年生の時は作曲編曲合わせて100曲以上やってました。計算すると3日に1曲書いてるんですよね、今考えたら大変なことだ(笑)
それは大変なペースです。
でも大変といえば浪人の時も大変でしたよ。
音大を受けるのなら普通の大学もきちんと受験するように親に言われました。
予備校に行って、理系難関校クラスに通って…。
音楽を勉強する時間はあったんですか?!
作ればあります。
空きコマに和声とか作曲をして、水曜は声楽と作曲、金曜はピアノを習いに行きました。
当時は今より20キロくらい痩せていましたよ。まあこの変化の原因は東京来てハマったとんこつラーメンと麻婆豆腐丼のせいでもあります(笑)
話を戻しますが、忙しくても頑張れたのは、やっぱり音楽がやりたくて仕方なかったからです。
現役生としての受験の時は、普通に大学に行って合唱団入って「あわよくば自分の曲をやってもらえればいいかな」と思ってました。
でも、せっかく自分が音楽をやってきたのにそれを生かさないのは勿体無いなと思ったんです。音楽は自分のルーツでもあるし。
そして後期試験にも落ちたあとに音大に行きたいということを親に伝えました。
親はびっくりしていましたが、父親から「大学選択のメリット・デメリット、10年後にどうありたいのか、自分の決意の強さを書きなさい」と言われ、A4用紙4枚をもらいました。
それを必死で書き上げて親に見せたら、「それは自分で持っておきなさい。頑張りな。」と言われました。
そうして、五教科九科目全部受けつつ、音大を受けて、進学した訳です。
だからこそ音大に来て、熱量のギャップにびっくりしました。
みんなそんな思いをして進学してる訳ではありませんからね…尚更ギャップを感じてしまいそうです。
そういえば、最初は合唱の曲を書きたくて作曲科に進んだんですよ。
それが今では合唱に加えて弦楽器や管楽器、ズーラシアブラスの編曲や作曲なんかもやらせてもらえています。音大に来たことで自分のできる幅がぐんと広がったように思います。
指揮科や作曲科は色々な楽器を触って、実際にどう使われているのかなど、実践をもって学んだ方がいいなと思いますね。
そういったことを知らない方が曲を書けるという人もいるかもしれませんが、守破離という言葉があるように、基本はしっかり抑えた方がいいと思います。
とはいえ、高校生の当時クラシックはあまり興味がなくて、とにかく合唱が好きだったんですよね!
自分の音楽プレイヤーのクラシック曲は、のだめカンタービレのアルバムのラフマニノフのピアノコンチェルトとチャイコフスキーの交響曲位しか入ってなくて。
あとスキマスイッチがちょっとと、その他すべてが合唱曲でした。
印象に残っている合唱曲はありますか?
僕が聴いて衝撃を受けたのは、東京混声合唱団が来ていたときに聴いた武満徹や、慶応ワグネルソサイエティの演奏…。そしてなんと言っても、全日本合唱コンクールの中部大会で愛知県立岡崎高校が演奏した、信長貴富作曲の「廃墟から」の第一章「絶え間なく流れていく」でしょう。
その演奏を聴いてから、学校にあるCDを全部聴いて、マニアの先輩からも借りて、それから音楽室の楽譜を借りまくって…
気づいたら沼にハマっていましたね(笑)
そうすると今度は自分で書きたいと思うようになりました。これまた合唱部の先輩に作曲をする人がいたので、それに触発されてやめていた作曲を再開しました。
受験の勉強を始めたのが遅くても、ずっと音楽の土壌はあったんですね。
そうですね。音楽を始めたのは、必然といえば必然だったんでしょうね。
作曲なんてね、どうやるんですかとか聞かれますけど、文章を書くのと変わらないです。日本語の代わりに音符で物語を紡ぐ、そういうのが作曲って事なのかなと思います。
西下 航平(にしした こうへい)
1992年宮城県仙台市生まれ、石川県白山市育ち。 東京音楽大学作曲指揮専攻作曲「芸術音楽コース」を首席で卒業後、東京音楽大学大学院音楽研究科作曲指揮専攻作曲研究領域修士課程を修了。2012年度、および2013年度東京音楽大学特待生に、また2016年度東京音楽大学大学院特待生にそれぞれ選ばれる。これまで作曲を池辺晋一郎、西村朗、原田敬子、鈴木敬、ピアノを山口泉恵、菅井千春、ヴィオラを升谷直嗣、声楽を水野賢司、中村昭一、指揮を野口芳久、薩摩琵琶を田中之雄、ジャズアドリブ奏法(ピアノ)をリック・オーヴァトンの各氏に師事。
400を超える幅広い編成の作編曲作品があるが、特に合唱作品やテューバ・ユーフォニアム作品が取り上げられることが多い。外囿祥一郎、次田心平、ダニエル・ペラントーニ、セルジオ・カロリーノの各氏をはじめとする多くの奏者に作品を提供し、高い評価を得ている。近作にはユーフォニアム奏者の外囿祥一郎氏、テューバ奏者の次田心平氏によるデュオ、「ワーヘリ」より委嘱を受けて書かれた「空飛ぶペンギン」(Euph.,Tuba,Pf.)(東京ハッスルコピー)、The premiere vol.4のために書かれた女声合唱とピアノのための「熟れる一日」(カワイ出版)、男声合唱団益楽男グリークラブの委嘱を受けて書かれた男声合唱とピアノのための「天球の調和」(Miela Harmonija)、中部フィルハーモニー交響楽団バストロンボーン奏者の森川元気氏の委嘱による「バストロンボーンとオーケストラのための協奏曲」などがある。Miela Harmonija、カワイ出版、オクタヴィア・レコード、スーパーキッズレコードなどから作編曲作品の楽譜・CDが出版されている。2017年よりズーラシアンブラスに代表される株式会社スーパーキッズの演奏団体「音楽の絵本」にも作編曲作品を提供している。
また指揮者としても活動し、2013年にはサクソフォン四重奏とオーケストラのためのコンチェルトを自身の指揮で初演(演奏:時宴フィルハーモニックオーケストラ)。2016年には山岡秀和作曲、ジャワガムランアンサンブルとオーケストラのための”then, the cat said "mew"”を、2017年には原田敬子作曲、「弦楽五重奏とオーケストラのための音楽」を指揮・録音するなど、現代作品の初演や録音も積極的に行っている。
ピアニストとしては水戸の名手・名歌手たち 第24回に伴奏ピアニストとして、また2012年より東京外国語大学コール・ソレイユの伴奏ピアニストとして演奏会に出演するなど、ソロ・アンサンブルなどの伴奏ピアニストとして活躍している。また2015年には薩摩琵琶奏者としてマレーシアのクアラ・トレンガヌで行われた国際ガムランフェスティバルに出演、伝統音楽同士のコラボとして高い評価を得た。
ヒューマンハーモニー・オーケストラ(神奈川県川崎市)、アグレント管弦楽団(神奈川県海老名市)常任指揮者。益楽男グリークラブ(埼玉県浦和市)客演指揮者・ピアニスト。日本コミタス音楽協会会員。アルメニア友の会会員。
2017年3月25日には、自身の合唱作品による個展演奏会が川口総合文化センターリリア音楽ホールで開催され、好評を得た。
趣味は温泉旅行と日本酒飲み比べ。好きな色は緑色。修士研究テーマは「アルメニア国民楽派のリズムとモードにみられる特色~アルメニア人作曲家の器楽作品における民謡との関連~」。 アラム・ハチャトゥリアン、アルノ・ババジャニアン、アレクサンドル・アルチュニアンに代表されるような、すぐれたアルメニア人作曲家の知名度を高めるべく日々努力している。