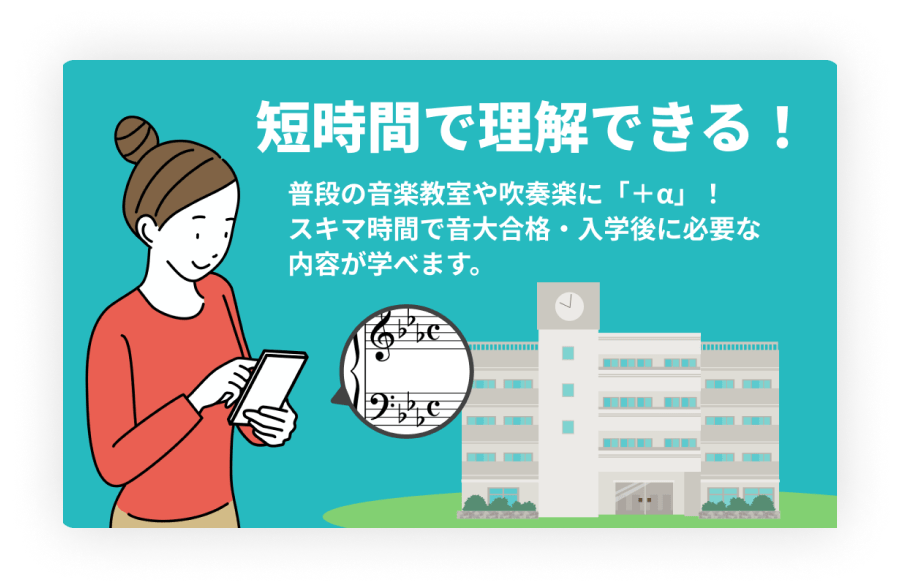菅沼起一さん
2018-08-24
今回は、京都府出身で、東京芸術大学でリコーダーを専攻された後、大学院では楽理科へ進路を変更され、現在も博士課程に在籍されている菅沼さんに、受験に関するお話や、あまりなじみの無い古楽についてなど、さまざまなお話を伺いました。
ちなみにあらかじめお伝えしておきますが、今回のインタビュー、過去最大のボリュームとなっております。
心してお読みください!
誰もが音楽の授業で触れる「リコーダー」ですが、音大で専攻する人は珍しいと思います。リコーダーをはじめられたきっかけなどを教えてください。
リコーダーを専門的に勉強したいと思う人って2パターンいると思っています。1つは、リコーダーを吹くのが好き、という人。たとえば中学や高校でリコーダー部に所属していた人とか...学校によっては「リコーダー部」ってあるんですよ。それにコンテストも。芸大に来る人はそういう人がほとんどかな。
もう1つのパターンは、私含め、古楽をやりたくてリコーダーを始めた人です。リコーダーはもちろん、古い楽器をやりたい人。私は古楽の演奏を初めて聴いた時に、自分の肌に合うなと思ったんです。例えば...恐竜が好きな子っているじゃないですか。私の場合だと、より古い時代に生きていた三葉虫のほうが好き、みたいな感じですね(笑)。魚に例えると、より深い海で暮らしている深海魚のほうが好き、みたいな。いわゆる一般的なクラシックレパートリーである18~20世紀の音楽よりも、もっと古い音楽が好きだなと思いました。
そこで、日本で一番身近な古楽器であるリコーダーを習い始めました。たまたま京都に本格的にリコーダーを教えられる先生がいらっしゃることを知ったので、中学2年生の春から習い始めました。リコーダーを始めようと思った時点で既にいろいろと調べ、東京芸術大学に古楽科のリコーダー専攻があることを知ったので、その時から芸大に進学しようと思っていました。芸大受験に向けてレッスンを受けていこうという運びにはなったのですが、実は高校は、音高のチェンバロ専攻として入学したんです。
リコーダーではない専攻に?
はい。まず、私がもともと通っていた中学校が、中高一貫の進学校だったんです。京都にある音楽高校にはリコーダー科が無かったので、高校もエスカレーターでそのまま進学しようとしていました。ただ、勉強と芸大受験の両立は大変だろうなと思っていたんです。
そしてなんとなく、もう一度京都の音高のホームページを見直していた時に、チェンバロ専攻が開設されていたことに気がつきました。どのみちチェンバロは古楽科の受験の必須項目なので(注1)、音大受験を目指して進学してきた子たちに囲まれた環境の方が芸大受験に適していると思い、急遽ですがその音高を受験することにしました。中学3年生の秋だったので、かなりギリギリでした。
運がいいことに、近所にチェンバリストの方がいらっしゃったんです。その人のもとで、3ヶ月ほど慌てて練習しました。普通は3ヵ月で音高を目指すのは無茶なので、良い子は真似しないでください(笑)。
確かに...3カ月で間に合った菅沼さんが異例ですよね(笑)。
もともとピアノは習っていたので、鍵盤楽器自体は弾けました。でもチェンバロとピアノは全然違います。鍵盤の重さや、音が出るシステムが全然違うんです。全くの別物なので、それに慣れるのが大変でした。受験には間に合いましたが、入学してからが大変でしたね。
音高時代のお話を詳しく聞かせてください。
音高の3年間は、学校ではチェンバロを学び、学校外ではリコーダーを習いに行くという大変な生活でした。練習時間の確保が特に大変で、15時に授業が終わった後、17時の下校時間まで2時間チェンバロを練習し、帰宅して夕飯後の19時半頃から、家の音出し可能時間である22時までリコーダーを練習、次の日も7時に家を出て、8時から始業まで学校で朝練、という生活でした。高校生って元気ですね。今なら絶対できません(笑)。
すごいですね。では、全然遊べなかったのでしょうか?
いえ、めっちゃ遊んでいた記憶があります(笑)。矛盾するようですが、「逃げずに練習する。でも遊ぶ。」みたいな感じかな。練習の間は練習するけど、疲れたら練習室を出てみんなとしゃべったりもしたし、逆に一人でもくもくと練習する時もあるし、眠たければ寝るし...休むのは本当に大事です。
私は筋肉や体が硬いタイプだったので、力んで練習するとすぐに疲れてしまうんです。チェンバロのタッチに慣れるまでは、とても力んでしまっていました。本当は全然力のいらない楽器なのですが。腱鞘炎になりたくなかったのと、現実的にしんどいという理由で、疲れたらすぐに練習をやめて休んでいました。なんだかんだでうまいこと切り替えられるように工夫していたのかなと思います。練習のしすぎで体を壊すと元も子もないですからね。
メリハリをつけることってやっぱり大事ですね。
そうですね。あとは、やるべきことをちゃんとやる、ということでしょうか。私の先生は、「来週までにこれを直してきなさい。」とかは言わないのですが、「ここをこうしてみたら?」という指摘は当然受けるので、そういうことは次の週までに絶対に直すように心がけていました。楽譜に書き漏らしたことをすぐに思い出してさらってみたりとか。
それから、ただやみくもに練習しない、ということも大事かもしれません。自分の中で何を次のレッスンまでにできるようにするか、というのをクリアにして練習すると、意外と時間はかからないのかも。私、効率主義なんですよね。一つの目標に対して、最速最短で取り組みたい。レッスンが多かったこともあり、かなり予定を立てて取り組んでいました。チェンバロのレッスンが月に4回と、リコーダーのレッスンが月に2回、計6つのレッスンをうまくさばけないといけなかったので。次のレッスンで前回の指摘が直せていないと、1週間何をやっていたの?ということになります。
それだけのレッスンをこなすとなると、譜読みも相当大変だったのでは?
譜読みは大変でした。高校の時は、チェンバロの譜読みとリコーダーの譜読み、そして音高の副科ピアノの授業も週1であったので、それも練習しないといけませんでした。チェンバロ専攻とはいえ、同じ鍵盤楽器ということで、ピアノ科並みのことを要求されました。厳しかったですが、おかげで指はまわるようになりました。当時はショパンのエチュードなども弾けたんです。リコーダーやチェンバロよりも、ピアノの譜読みの方が大変だったかもしれません。
リコーダーで受験を目指す菅沼さんにとって、チェンバロ専攻としての音高生活は、モチベーションを保つのは難しかったですか?
はい、高校1年生の時にモチベーションを崩しかけました。もともとリコーダー専攻を目指している中でのチェンバロ専攻だったので、不真面目だったんです。それで結構問題にもなったり...
でも、音高って3年間で意識が変わるんです。受験が近づくのはもちろん、コンクールなどもどんどん受けるので、みんなが音楽専攻生としての生活になっていきます。そういう環境にいると、ちゃんとしなきゃと思うようになりました。自分の中に、音楽専攻生としての生き方やメンタリティが刷り込まれていきました。なのでグレることもなかったですね。というかそこでグレていたら、今は芸大にいなかったと思います(笑)。
高校3年生になると、チェンバロの成績もよくなりました。この環境に身を置いたのは正解だったと思います。周りのみんなも芸大に行くモードだったので、直前に試演会をやったり、芸大のソルフェージュ試験の対策会をしたり、モチベーションが整えられました。上手な人が多かったですしね。3年間かけて受験準備をした、といった感じです。
そうして見事、芸大に合格された菅沼さんですが、芸大に入ってからはどうでしたか?
苦労しました。音高時代にはプロとして演奏することはありませんでしたが、大学では、プロになるためのいろいろな社会的選別が始まりました。仕事がきたりこなかったり、そういうことをこなしながら、自分の実技のスキルも伸ばしていかないといけない。
進路選択を考える時、プロのリコーダー奏者になるためにはどういう準備をしたらいいのか、いろいろ考えました。そしてリコーダーのテクニックをもっと高めないといけないと思い、ひたすら練習しました。芸大の先生の勧めで、外部のレッスンにも通いました。またレッスンだらけの日々で、さらう曲もたくさんありました。もっと遊べばよかったと後悔しています。学部時代は土日もずっと練習していたのですが、あれは不健康な過ごし方でしたね。だからこそ今の演奏技術がある、といえばそうなのですが。
学年があがると外の仕事も入ってきますし、私自身もやりたがりなので、いろいろな自主企画の演奏会をしていると、遊んでる場合じゃなくなりました。当時の自分にとっては必要なことだったのかな...でもやっぱり遊んだほうがよかったかな...うん、遊んだほうがいいですよ(笑)!高校時代に比べると、大学の方がシリアスに過ごしていたと思います。自分がプロとして社会の中で生きていくために必要なことを準備していく4年間でした。
菅沼さんの自主企画といえば、ユニークなものが多いですよね。
最近はそうですね。「ぼっち企画(注2)」とか。とりあえず名前で覚えてもらうのが大事だなと思っているので、キャッチーなタイトルを意識しています。よくあるコンセプトやタイトルはみんながやっているので、私は違うことをやりたい、というのはすごくありますね。
おかげでよく、「タイトルが変」など言われるのですが、私自身は実はそれほど変だと思っていません。映画のタイトルなどでよくあるじゃん!と思っています。プログラムについても指摘されることはありますが、実はちゃんと元ネタがあって、他のものからインスパイアされて企画しているものばかりなんです。無から生み出しているものは基本的にはないかな。映画とかアニメとか、他に好きなものが多いので、そういうものの中からいいなと思うものを持ってきたりしています。
幸い、一緒にやってくれる友人も多かったので、学部時代から自主企画はよくやっていました。もちろん人から依頼されたこともやりますが、年に一回は、最低でも自主企画の演奏会をさせてもらっています。東京は古楽の愛好家の方も多いので、変なことをやると面白がって来てくださることが多く、とても感謝しています。
「古楽」と聞くと、保守的な方が多いと思っていました。
古楽って、いわゆるクラシック音楽の伝統的な部分に、「そうではないんじゃない?」と切り込んでいく、尖っている部分もあるんです。新規性のあるもの、変わったことに面白さを見出している方が多いので、私の変わった自主企画はそういう面でご好評をいただいています。
だからなのか、現代音楽の界隈とも古楽界は仲が良くて、私も現代音楽を演奏するので、現代音楽のファンの方が古楽の演奏会に来てくださる、ということもあります。どちらの界隈も、先鋭的かつ前衛的なものが好きだし、それがわりと日常で、空気のように流れているんですよね。そういう方々は、いわゆるクラシックの演奏会を聞きに行く人とは少し違うのかも。もちろん、どちらも好きな人もいますが。
たとえば、古楽の人はラフな演奏会が聞きたいという話を聞いたことがあります。だから古楽をやるようになってからは、ドレスを着なくなった、なんて話も聞きますね。ラフな雰囲気を演出するために心を砕いたりすることが多いかな。そのほうが楽しんで聞ける、という方が多いので。これまでにいろいろとやってきた経験則で、今も試行錯誤しながら自主企画に取り組んでいます。
大学院では、またしても専攻を変更されたとか。
はい。大学院からは音楽文化学へと専攻を変更し、修士、博士と進学しています。芸大に在籍して8年目になりますね。今は、演奏と研究の二束のわらじ状態です。
学部時代は、とにかく練習しなきゃと思っていた一方で、勉強したいとも思うようになったんです。もともと古楽って「自分が演奏する時の演奏解釈の論理的土台を、歴史学的アプローチに依拠する方法論」なんですね。そうなった時に、昔のこと、当時のことをちゃんと勉強していたり、知るリテラシーがないと、やっぱり演奏がどうしようもないなと思うようになっていきました。練習すればするほどそういう思いが強くなっていったんです。なので、大学院では演奏ではなく、研究の方へ進路を変更しようと、学部のかなり低学年の時から決めていました。楽理科(注3)の授業にもぐりこんだりもしましたね。
大学院の試験はどうでしたか?
大変でした。楽理科として勉強してきていない人間が楽理科の人と同じ試験を受ける難しさは想像を絶しました。まず、辞書持ち込み禁止の外国語の試験が2言語あります。それから修士課程での研究計画と、それに対する口述諮問。そして音楽学の試験です。
音楽学は、5つの領域(音楽美学、西洋音楽史、音楽理論史、日本東洋音楽史、音楽民俗学)から2つを選択し、それぞれ3つずつ設問があるので、そこからさらに2問ずつ選択して、1問につき800字で論述する、といった内容です。2時間で計3200文字、考えている時間はほぼなく、条件反射で書かないと間に合いません。えげつなかったです。対策として、過去問をひたすら解きました。何十年分の過去問を解いていくと、おおよその答え方や出題の傾向がわかるようになるんです。夏前までは、どんな設問を見ても「知らんやん!」という感じでしたが、先輩方が助けてくださったおかげで、なんとか合格することができました。
でも大変すぎて、ストレスからくる胃腸炎になってしまったんです。しかも受験の1年後に。私のかかった腸炎って1年後に症状が出るらしくて、病院で発覚しました。先生に「1年前に何かありましたか?」と言われて、「院試だー!」とすぐに気がつきましたね。約2ヶ月間、朝から晩まで部屋にこもって勉強していたからかな。
博士過程にまで進学されたのは、もっと研究を続けたいと思ったからなのでしょうか?
修士に入った時点で、博士も進学するつもりでいました。将来、何になりたいか考えた時に、2足のわらじを履こうと決めたんです。研究者としてのキャリアを積みながら、演奏家としても活動していこうと。
よりよい演奏をしたいから勉強したいと思ったので、どちらかをやめるというのは、最初の動機とズレると思うんです。とても大変ですが、研究をするようになったおかげで、これまで演奏できなかったことができるようになりました。変わった活動ができるのも、研究活動のおかげだと思います。演奏しているだけじゃ見えない視点が山のようにあるし、研究している内容が演奏に応用できることがたくさんあるんです。
古楽をやるうえで、そういう勉強的なことは必要不可欠だと思います。「練習する時間無いじゃん!」「原稿書く時間無いじゃん!」となることもありますが、でも高校の時からそんな感じだったので。そういう性分なんだと思います。本当はもっとゆったり生きたいのですが...ですので、研究したい人には楽理科はおすすめです!
菅沼さんのコンサート情報ではよく「ディミニューション」といわれる、メロディを分割して変奏していく演奏技法を目にするのですが、この技術はどのようにして取得されたのでしょうか?
古楽が好きだったので、中高時代は沢山のCDを聞いていたのですが、その中でも特に、ルネサンスの「ポリフォニー」という、多声声楽曲が大好きだったんです。
当時の楽器のプレイヤーは、それに派手な装飾をつけくわえてアレンジをしていたのですが、そのアレンジの譜面が残っていて、現代の人がその譜面を使用して演奏をしているCDに出会いました。すごく格好良くて、「もともと好きだったルネサンスポリフォニーがなんかすごいことになってるー!」って思いました(笑)。
そしてまたしてもご縁があったのですが、京都に「コルネット」という角笛型の楽器のプレイヤーさんがいて、この楽器は17世紀以前に最も使用されていた楽器のため、コルネット奏者のレパートリーがまさに、ポリフォニーに装飾をつける、といった音楽だったんです。そのノウハウを沢山ご存知だったので、その方にいろいろと教わりました。当時のハウツー本があるので、それを見せていただいたんです。その本があるおかげで、現代の私達でも演奏ができます。すっかり大好きになったので、今でもずっと演奏していますし、研究対象にもなっています。
菅沼さんは、近所に専門家の方がいらっしゃった、ということが多いと思うのですが、その方々とはどのようにして繋がりを持ったのでしょうか?
その方の演奏会のチラシに連絡先が載っているので、そこにメールしました。でも、なんて面の皮の厚いことしてたんだろう私!と思います(笑)。今ならメールを送るのに1~2カ月はかかりそうですが、当時は思い立ったらすぐにメールをしていました。
最後に、このインタビューを読まれている方にむけて、メッセージをお願いします。
自分がその対象に向く心、モチベーションがあるのなら、それは絶対に信じた方がいいです。自分を正しく突き動かせるのはそれだけかな。
でも、「好きなら大丈夫」というのは違うと思っています。私は他にも好きな事はありますが、だからといってそれを職業にしたいとは思わなかったんです。好きだけじゃやっていけない、という感じ。心が向くかどうかです。私は、心が向いたのが古楽でした。嫌なこと、ままならないことも多いですが、だから続けられています。
それから大事なのは、とりあえずやってみること。あとは、できるかな?と思わない。やれるかどうかは、やった時の自分で決まります。やる前の自分では決まりません。やってみて「めっちゃ大変だった!」とか「やっぱだめかも。」と思うことはあるだろうけど、でもやり始めないと、それすらもわからないから。
私は特に「やりたい」を大事にしています。To doリストの他にもう一つ、want to doリストを作るんです。多幸感に溢れたリストになって、やる気のモチベーションになりますよ。
注釈
注1「チェンバロは古楽科受験の必須項目」
芸大の古楽科学部入試には、専攻実技の他、チェンバロによる通奏低音課題(数字付き低音:バスの旋律に和音を示す数字がふってあり、それを見ながら和音を付けて演奏していく)といったものがある。
注2「ぼっち企画」
《菅沼起一の一人でどこまでできるかな?》(6月24日、えびらホール)。
リコーダー無伴奏作品のレパートリーを集めた独演会。演奏者本人による濃厚トークコーナー、プログラムを明かさず演奏するクイズ的構成、聴衆参加型演奏コーナーなど、豊富なコンテンツを取り揃えた公演として企画された。
注3「楽理科」
東京芸術大学音楽学部にある専攻のひとつ。音楽研究の学である音楽学(西洋音楽史、日本・東洋音楽史、音楽民族学、音楽美学など)を研究・教授し、将来、音楽の学問的研究およびそれに関連した仕事にたずさわる人材の養成を目的としている。
〜菅沼 起一(すがぬま きいち)〜
京都府出身。京都市立音楽高等学校(現:京都市立京都堀川音楽高等学校)チェンバロ専攻を経て、東京藝術大学音楽学部古楽科リコーダー専攻卒業。これまでにリコーダーを山岡重治、太田光子、中村洋彦の各氏に、チェンバロを三橋桜子、澤田知佳、廣澤麻美の各氏に師事。後に音楽学専攻へと転向し同大学院修士課程を修了し、大学院アカンサス音楽賞を受賞。現在、博士後期課程に在籍し学内外で学会発表、論文・CD解説・プログラムノート等の執筆を精力的に行うと同時に、中世からバロック、新作初演に至る幅広いレパートリーでの演奏活動を展開中。