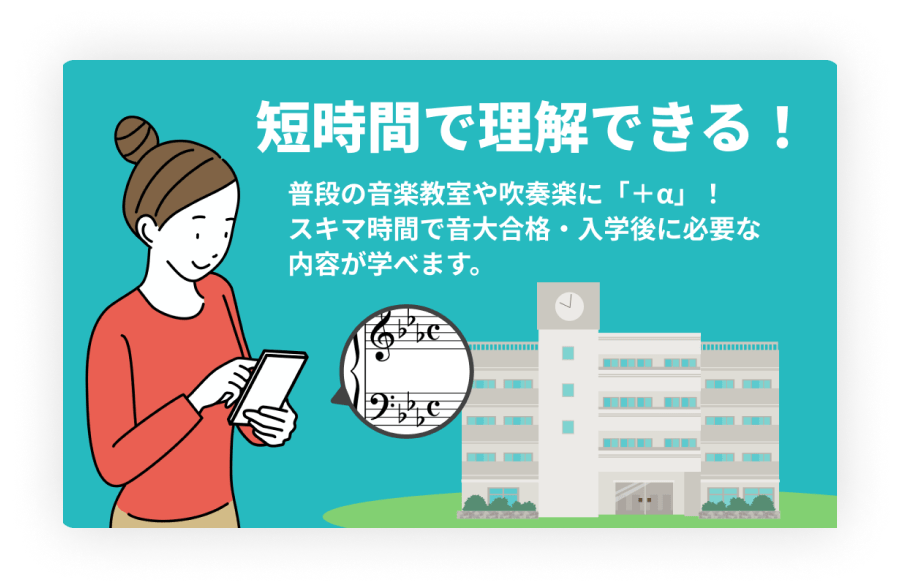高橋郁美さん
2018-08-24
今回は、東京芸術大学の音楽環境創造科を経て、現在は音響関係のお仕事をされている高橋さんに、通称「音環(注1)」を受験されたきっかけや、卒業後の進路のことなど、さまざまなお話を伺いました。
音環を受験しようと思ったきっかけを教えてください。
もともと音響に興味がありました。なんでだったかな。テレビか何かで見て、面白そうだなと思いました。ドキュメンタリーや舞台裏などを見るのが好きで。最初に見たのは確かレコーディング風景だったと思います。面白そうだなと思ったんです。そして高校で文理選択をする前くらいに、芸大に限らず、音響系の学校を探し始めました。
高校は普通科の進学校でしたが、たまたま私の学年は、10人くらい芸術系の大学を目指す人がいるという特殊な状況でした。そのため学校が、一般大学を受ける人とは別の時間割を作ってくださったんです。みんなが日本史などの授業を受けている時間に、私は音楽の授業を受けていました。その中には東京芸術大学を志望している人が多かったので、そこまで芸大に固執していたわけではありませんが、なんとなく芸大を意識はしていました。
受験対策はどのように行ったのでしょうか?
芸大受験生向けに作ってくれた音楽の授業で、楽典の勉強や新曲視唱の練習をしました。また、音環の入試における点数配分は、全部で1000点のうち、センター試験が500点、つまり半分を占めるので、センター試験がとても重要です。そのため高校3年生の夏くらいから、英語だけ予備校に通いました。
小論文や面接の自己表現についても教えてください。
自己表現で何をしたかはちょっと言えません(笑)。
小論文は、基本的には自分で準備をしました。「過去にはこういう課題が出題されたのか。」「こういうテーマがありそうだな。」みたいなものを、インターネットなどで確認していました。
ただ、受験のシステムが私の年から変わったので、それほど情報が無い状況でした。情報が無いのはみんな一緒なので、点数配分の高いもの、つまりセンター試験できちんと点が取れれば大丈夫だろうと考えていました。ですので小論文の指導はちゃんと受けていませんし、入試でちゃんと書けた記憶もないです(笑)。
小論文のために必要な音楽の知識も、音楽史の勉強をしていくなかで得た知識でまかなっていました。それが正しい小論文の書き方なのかはわかりませんが。
とにかくセンター試験が大事、ということでしょうか。
ただ、今は私達の年に入試のシステムが変わってから7、8年経っているため、私と同じような対策でいけるかはなんとも言えません。先生方もそろそろ入試慣れしていると思うので、面接で「この子とったらまずいな。」とか「この子いいな。」と思うかもしれませんし、問題の作り方もいじわるをしてくるかもしれません。わからないですけどね。
私は入試のシステムが変わった最初の年だったので、ラッキーだったのかもしれません。以前はもっと配点などがフワっとしていましたが、現在は音環入試における配点を公開しています。センターが半分を占めるというのは、芸大の中では特殊ですね。
そして芸大に合格された高橋さんですが、芸大に入ってよかったことはありますか?
楽しかったです。自分の知らない世界を知ってる人がいっぱいいるので。それまではクラシックなども全然なじみが無かったですし。美術の人達もです。いろんな人達といろんな制作をできたのが楽しかったです。ミュージカルを一緒にやったり、映画を一緒に作ったり。
一般大学でいうところのゼミに相当する「プロジェクト」では、音響系の研究をおこなうプロジェクトを迷わず選択しました。入学してすぐにプロジェクトを選択するのではなく、まずは幅広く勉強してからプロジェクトを選択するカリキュラムなので、芸大の他の科よりは、いろいろと考える時間があるかもしれません。
プロジェクトを選択した後、それを変更する人もいます。入学時に必ずしも他の科のような高度な専門知識や技術が必要というわけではない、というのも、音環のいいところだと思います。
高橋さんが選択された音響系のプロジェクトについて詳しく教えてください。
音楽や音を主体とする録音制作や、音響に関する研究をおこなうプロジェクトで、同じプロジェクト内でもいろいろな人がいます。私は主に、映像と関連づいた音響活動をしていました。
他の人だと、レコーディングが好きな人や、研究、実験を中心にする人もいました。先生的には、何をやってもいい、というスタンスでした。専攻やコースにしばられることがないので、やりたいことがしやすい環境かもしれません。音楽に関することを、少しずつですが一通り、授業だったり自分の制作でいろいろ勉強させてもらえました。
逆に、芸大のマイナス面などは何か感じますか?
卒業してから一般社会になじめない人が多い印象があります。一般企業に就職していくのが難しいです。先々のことを考えると、いろいろ大変なことが待っている気がします。就職活動は難しいです。
まず大学が東京芸術大学という時点で、「じゃあなんでうちを受けるの?」と必ず聞かれてしまいます。芸大の就職率は一ケタで、その中で音環が25%くらいだったかな、それで高いと言われるレベルです。就職という文化が芸大にはありません。なので自分で頑張らないといけないです。とはいえ、私もそんなに頑張って就職活動をしたわけではないのですが...
高橋さんの就活事情を教えてください。
就活の時点では、音響の仕事につこうとは思っていませんでした。就職は違うことでもいいかなと。ただ、他にやりたいこともありませんでした。3社くらい適当に受けて、そんなだから当然受かるわけもなく...でも当時のバイト先などでも25歳、30歳フリーターという人もいたので、そんなに焦っていなかったです。
そうしたら教授のほうが焦って(笑)。教授と昔なじみの人がやっている会社の方を紹介してくださり、そこに就職が決まりました。音響系の会社です。卒業する直前の2、3月頃に決まったのでギリギリでした。もしそこで決まらなかったとても、実家暮らしということもあって、そこまで深刻には悩んでいませんでした。
音響系のお仕事って、どういうことをされるのですか?
私の場合は、音響効果をつけていく作業や、MAと呼ばれる、ナレーションの収録や音量を調整する作業をしています。テレビCMや、youtube動画の冒頭に流れる広告系、イベント時に店頭で流れる音楽や社内向けのものを以前は担当していましたが、今は転職して、主にドラマのMAを担当しています。
今後の目標を教えてください。
今の仕事は、泊まり現場やスケジュールが読めなかったり...ということが多い、かなり不規則な仕事です。この生活を何歳まで続けられるんだろうという感じなので、なるべく健やかな生活を送りたいです。
音環をはじめ、音大受験を考えている方々に向けて、メッセージをお願いいたします。
音環は楽しいですが、入ってからさまよう人も多いかもしれません。「好きなだけでよかった。」という感じでしょうか。たとえ音楽が好きだとしても、技術を極めるというよりは研究をする機関なので、研究として考えた時に、興味を持てることがあるかどうかが重要になってきます。
音楽を仕事にするのか、学問でやるのか、趣味でやるのか...芸大をはじめ、音大などに入ってしまうとこの業界から出づらいことは確実なので、それは念頭に置いた方がいいと思います。
注釈
注1「音環」
音楽環境創造科の略。東京芸術大学音楽学部にある専攻のひとつ。21世紀の新たな音楽芸術と、それにふさわしい音楽環境・文化環境の発展と創造に資する人材育成を目指している。
~高橋 郁美(たかはし いくみ)~
神奈川県出身。東京藝術大学音楽学部音楽環境創造科卒業。AES Japan Section 60th Anniversary, 2013 学生サウンドアウォード 第6回 サウンドデザイン部門 最優秀賞受賞。これまでに亀川徹、丸井淳史各氏に師事。フジテレビ、BSジャパンなどの連続ドラマに携わっており、現在はAbema TVで放送中の「星屑リベンジャーズ」を担当している。