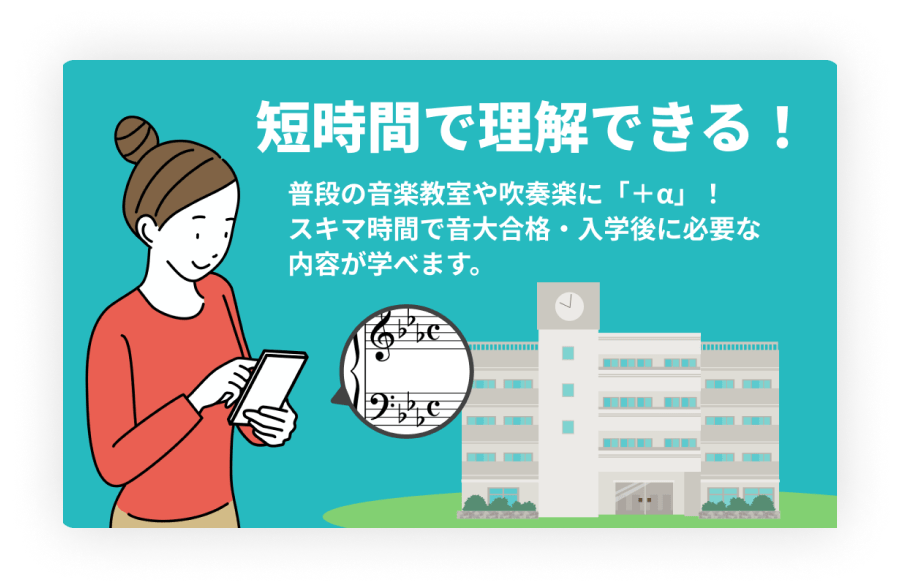上野能寛さん
2018-10-05
今回は、東京芸術大学邦楽科で能楽を専攻した後、現在は内弟子として研鑽を積まれている上野さんに、能楽に関するいろいろなお話を伺いました。
能楽をはじめられたきっかけを教えてください。
私が小学生の頃に亡くなった祖父が、プロの能楽師でした。ですので、能で使う道具などが常に身近にある環境でした。でもはじめはそれほど興味がなかったので、遊び感覚で能に触れていた感じです。私の叔母も、家元に許可をもらって師範として能楽を教えているのですが、祖父が死んだ後に、叔母から祖父の話をいろいろ聞きました。祖父はもともと公務員だったのですが、それをやめて能楽師になったそうです。世襲制の家が力の強い伝統芸能の世界では、素人出は受け入れられないことも多いので、プロになるために祖父は相当の苦労をしたと思います。そういった話を聞いているうちに、祖父が死ぬ気で努力したであろうことを想像するようになって、それがなんとなく心の片隅にひっかかるようになって...そして高校2年生の時、部活をやめたことをきっかけに、祖父の能楽を継ごうと思いました。そこから本格的に叔母に習いだして、東京から九州に教えに来てくださっている先生に弟子入りしました。
芸大の邦楽科って、どのくらい難しいのでしょうか?
邦楽全体がそうかはわかりませんが、私の感覚だと、入ること自体はそれほど難しくないと思います。倍率が低くなってきているというのと、プロの家系でずっと勉強してきた人をのぞけば、飛びぬけて上手な人というのは高校生の段階ではあまりいないことが理由です。
私は能楽の実技よりも、センター試験の勉強の方が大変でした。もともと工業高校に通っていて、卒業後は就職する気でいたので...授業が専門教科ばかりなので、たとえば国語だと現代文の授業しかないんです。古文や漢文の知識が中学どまりでした。なので高校2年生から急遽、一般大学に進学するクラスにまざったりしましたが、とにかく勉強が結構大変でした。
その後、芸大に合格された上野さんですが、芸大に入ってよかったことはなんですか?
芸大でよかったことは、多方面に知り合いができたことです。能は、重要文化財として国に守られてはいますが、単体では需要が下がってきています。能は削減、削ってきた芸能なので、今の時代に受け入れられるものとしては色が違うのかもしれません。たとえば歌舞伎の動きは派手なものが多いのに対し、能は、動きを小さく、最小限のもので表現する、無駄なものを全部切り取っていく、という考え方で完成した芸術です。昨今は派手なもの、わかりやすいものが人気となっている様なので、能も今の時代に噛み合わないといけないと思っています。そういうことを考えた時に、芸大時代にできた繋がりのおかげで、いろいろなことにチャレンジしやすくなっています。先日は芸大の先輩が企画をしてくださった舞台で朗読劇とコラボしたのですが、すごく刺激を受けました。
今のままの形では能楽は衰退していってしまうので、それを巻き返すためにはいろいろなものを取り入れたり、コラボをして能楽を知っていただく、そこからではないかと考えています。
そういう面で東京芸術大学などでの交友関係は私の財産となっています。
その他には、それぞれの専攻でその道の最先端で活躍されている一流の先生方からご指導いただけるので、それが今の自分の糧となっています。さすが芸大ですね(笑)。
逆に、芸大で苦労したことはなんですか?
受験以上に、入学してからが大変でした。今までやってこなかったこと、自分の専攻外の邦楽の楽器を一通り学ばなければならないので、それがキツかったです。私が素人出ということもあって、家の出の人に比べると差もありましたし、とにかく覚えることが多かったです。
上野さんは能楽専攻ですが、能楽の中でもいろいろ種類があるんですよね。
はい。私は「シテ方」という、主人公を演じるための修行を積んでいます。他に、「ワキ方」「狂言方」「囃子方」という役割があります。ワキ方は、主に物語を進行する役の方々のことで、脇役という言葉はここからきています。狂言方は、能の前場と後場をつなぐ役割を持っています。野村萬斎さんなどが有名ですね。囃子方は、能舞台後方で楽器を演奏している方々のことです。私はシテ方の宝生流という流派に所属しています。シテ方の流派は五流ありますが、芸大には観世流があります。
能楽の稽古ってどんな感じなのでしょうか?
西洋音楽と違って五線譜が無いので、高さが明確に決められていません。楽譜の代わりに台本がありますが、上とか下とかしか書かれていないので、先生に唄ってもらって、それを聞いて唄います。基本的に耳で覚えます。「もっと上、もっと上、ちょっと行き過ぎ、もっと下。」みたいな指導です。その繰り返しですが、続けていくと、だんだんわかってきます。
能楽師になるための流れ、みたいなものはあるのでしょうか?
我々シテ方宝生流に関しては、たとえプロの子供であっても、芸大に行って、卒業後にご宗家の内弟子になる、という流れが一般的です。芸大を卒業する時に、内弟子に入るか入らないかをご宗家に聞かれます。私は現在、能楽堂に住み込みで内弟子をしています。家元の補佐をメインに、稽古をしたり、舞台経験を積んで修行をしています。
ご宗家や家元というのは、芸大時代についていた師匠のことですか?
そうではなく、家元というのはその流儀のトップのことです。私は一浪したのですが、そのころから師匠は変わっていません。ただしご宗家の内弟子になると、ご宗家の弟子として扱われます。少しややこしいですね(笑)。
学部の3、4年生くらいに「楽屋入り」に声をかけていただけるのですが、そこで確実に芸大外の先生方と知り合いになります。狭い世界なので、楽屋に行けば流儀の先輩方が全員いるのです。
楽屋入り...とっても緊張しそうです。
楽屋入りは緊張します。でも基本的には何もさせてもらえません。装束のことなどがメインになりますが、一着あたり、絹はだいたい50年、いいものだと100年くらい使用するので、とても大切にしないといけません。なので学生には触らせてもらえません。基本的には内弟子が管理します。今は私も内弟子なので、能楽堂の蔵と呼ばれるところで、装束や面などを管理しています。
内弟子、というものは何年くらい務めるのでしょうか?
私の流派の内弟子は、人によってまちまちですけど、8年くらいが基本です。私は4年目になります。過去の最長記録では13年いた人もいるそうです。内弟子というのは必ずいなきゃいけない人達で、たとえば外部での公演がある際は、衣装やいろいろな道具が必要になるので、それを持ち運びする仕事など、他にもいろいろな業務があります。でも現在、私の下に誰一人入ってきていない状況です。今は内弟子は8人いますが、4月にまた一人卒業するので、下に新しく入ってこないとある程度で卒業のシステムが止まります。上がどんどん抜けていった場合、だいたい残りの内弟子が4、5人くらいの時点で止まります。そこで我々は固定になるので、下が入ってこないと卒業ができないのです。私は何年いたらいいのかわからないので、少し不安を感じています。もしかすると、一番長い13年の記録を超えるかもしれません。でも、この内弟子のシステムも変わるかもしれません。家元がまだお若くて、いろいろ考えてくださるとは思うので...それを踏まえても、内弟子期間は長くなりそうですが。
少しネガティブな話になってしまいましたが、内弟子という環境は、能の世界を勉強するうえでは最高の環境です。能楽堂に住んでいるので、いつも公演で使用している本舞台で、深夜に好きなだけ稽古ができます。でも10年以上はきついかな(笑)。後輩募集中です。ほんとにお願いします。
上野さんの今後の目標はなんでしょうか?
今は東京で活動していますが、九州ではうちの流派が、というか能楽が弱いので、ある程度東京で活動したら九州に帰って、いろいろなことをやりたいです。能というものを広げていきたい。近い目標としては、そのために毎日とにかくこなしていくということ。いろいろなことを覚えないといけません。覚えることしかない。能楽を頑張るしかないです。
最後に、読者の方へのメッセージをお願いします。
ご興味がありましたら、是非能楽を観にいらっしゃってください。格式高いと思われがちで、「見に行っていいのかな?」「服装どうすればいいのかな?」など聞きますが、静かに見てくださればそれで大丈夫です(笑)。気楽に観て、気楽にお声がけいただければと思います。そうしたら我々も嬉しいです。そんなに偉いものじゃないです。みんなちゃらんぽらんなところもありますよ。バチっとしているのは舞台の上だけです。お待ちしています。
もし将来、邦楽の世界に進みたいのであれば、実力だけでは難しいと感じる場面もあるかもしれません。家とか、そういう難しい部分がありますけど、でも最終的にものをいうのはやはり実力なので、本気でやれば必ず認めてもらえます。こちらに関してもやはり、気楽に、やる気を秘めながら、入ってきてください(笑)。
~上野 能寛(うえの よしひろ)~
平成4年生まれ。福岡県出身。20代宗家宝生和英、及び東川光夫に師事。平成27年東京藝術大学音楽学部邦楽科卒業。平成28年「草薙」ツレで初舞台を踏む。現在は、和英宗家のもと内弟子として修行中。